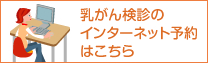院長の「JoJoブログ」
医療小説
2025-01-20 23:46:38投稿
片道25分の電車通学をしていた中学、高校のころ、電車の中で、いつも本を読んでいた私。始発から終点に近い行程だったので、ほぼ座席を確保できたことも幸いだったと思う。そのころ、とにかく一番好きだったのが、北杜夫の作品。彼を一躍有名にしたのが、「どくとるマンボウ航海記」で、精神科医だった彼が船医として航海したときのことをつづったエッセイだけれど、あまりにも面白くて、その後も彼の本をすべて読みつくした。多分、エッセイも小説も、私が高校卒業するまでに出版されたもので読んでいない作品はないと思う。北さんは、精神科医で小説家であったため、高校時代の私の将来の夢も、精神科医で小説家だった。
しかし、その後の私は、とりあえず、医者にはなったけれど、希望だった精神科医にはならなかった。
大学に入ってからは、卓球ばかりして読書からは縁遠くなり、わけのわからない日記と称した駄文はよく書いていたけれど、小説などを書くことはなく学生生活をおわり、産婦人科医になってからは、仕事と家事、育児で、夢は夢に終わったと思っている。
ただ、医師の中には、小説を書く人が結構いて、最近になって、医者で小説家という人の作品をよく読むようになった。実際、医療小説と呼ばれるものを書いている人は、まず医者なので、小説とはいえ、医学的知識のない人がこんな内容は書けないよなというのが文章のあちこちにみられる。かなり前に映画化もされた、”このミステリーがすごい”大賞にえらばれた、「チームバチスタの栄光」の著者、海堂尊氏は病理医(現在は執筆に専念)なので、手術のことが詳しく書いてあったり、司法解剖の微妙な描写などが、病理医だなぁと思わせる文章。
他にも私がこの10年くらいで読んだ小説の中で、医者だった人は
久坂部羊 午島志季 知念実季人 南杏子 中山祐次郎 等
いずれの作品も、医学的な描写や、医学部や病院の実情が細かくかかれており、医者の私としては、小説の場面がものすごくリアルに伝わってくるので、他の小説に比べて、読むスピードが速くなり、あっという間に読んでしまった。そして、医療小説をAmazonのkindleで買うと、次々と別の医療小説を”あなたにお勧め”とPCが勝手に言ってくるので、その策略にはまってしまって、またクリック。
あと小説家というより、東大出のお偉い産婦人科の先生のひとり、岡井崇氏(2017年没)が、産科医は無責なのに訴えられやすいという産科医療の問題点を世間の人たちに知らせるために書いた「ノーフォルト」は、20年前になるけれど、私にとっては、衝撃的だった。そもそも産婦人科の大学教授という立場で小説が書けるということ自体がとてもうらやましいというのが、まず第一。そして、当然のことながら最終的に産科医を応援したストーリーになっているいうこと、その後にドラマ化された、藤原紀香主演の「ギネ」は、ちょっと誇張された部分が多かったけれど、その当時お産ばかり診ていた私にとって、忘れられない小説の一つだ。
そんな医療小説を、よく読んでいる今日この頃、高校時代の夢、小説を書いてみたいなという気持ちが時々むくむくと湧き上がる。でもすぐに、登場人物は?ストーリーは最終的にどこにもっていく?などと考えると、あぁ、ムリムリムリ・・・となってしまっている。
小説ではなく、ハウツー本のようなエッセイのようなものなら書けるかも・・・と思ったこともあるけれど、そんな本を出している医者はさらに多くいて、読んでると単なるお説教のような気がして、(なら読むなってことだけど)結局自慢話?となってしまうこともあり、やっぱり本を書くって大変だなとなってしまう。
せいぜい、このブログを地道に続けて、Amazonのおすすめ本をちょこちょこクリックして読むのが精いっぱいの私。仮に小説を書いたとしても、世の中の人に読んでもらうまでに至るには、よほどのことがないと難しいし、お金もかかるしと思いながらすごすのでした。